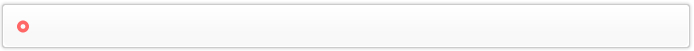
うつ・せん妄・認知症の人へのアプローチ -3Dサポートチームの事例にみる
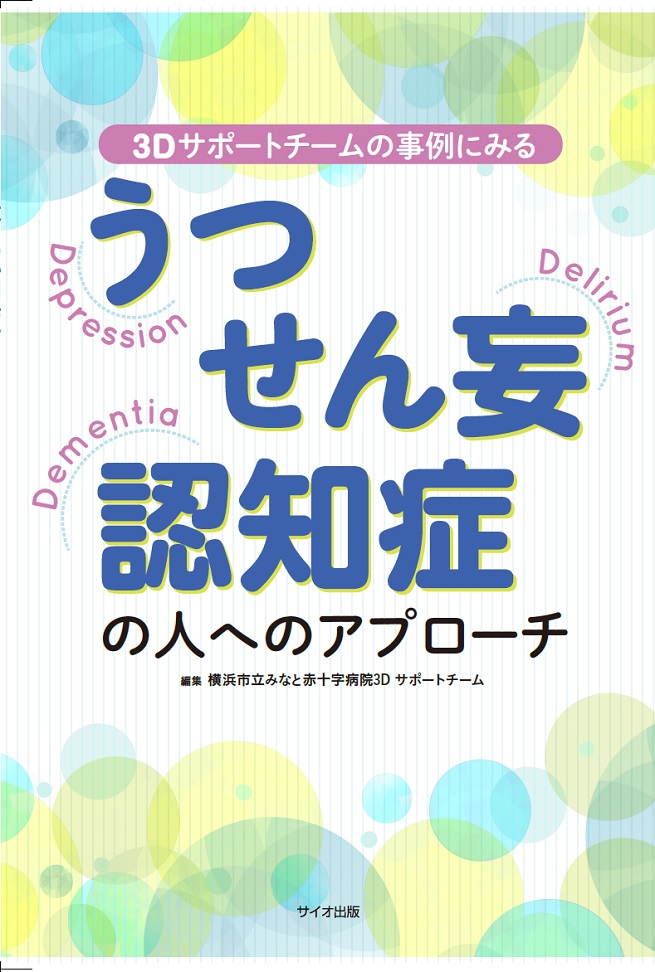 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
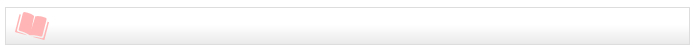
書籍概要
横浜市立みなと赤十字病院でうつ、せん妄、認知症の各症状をサポートしている3Dサポートチームの誕生の経緯と各症状の基礎知識を解説。またチームがかかわったさまざまな事例から鑑別のポイントを紹介する
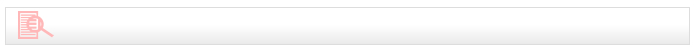
書籍目次詳細
第1章 多職種チームと看護管理
1医療の現状と多職種チーム活動
2当院における多職種チーム
33 D サ ポ ー ト チ ー ム 立 ち 上 げ の 経 緯 と そ の 効 果
4管理者として多職種チームを支援する
5「場」をつくり、「共体験」することで、「共感」の輪をつくる
6高齢者や認知症をもった人が安心して生きていける社会をめざして
第2章 3Dサポートチームとは
13D サポートチームの誕生の経緯
2活動内容
3多職種チームのメリット
4各専門領域の役割
1.リエゾンナースの役割
2.認知症看護認定看護師の役割
3.臨床心理士の役割
第3章 認知症・せん妄・うつ病の基礎知識と診断
認知症の基礎知識と診断
1認知症とは
2認知症の有病率
3認知症の症状
4認知症の診断
5認知症の原因疾患
6認知症の検査
アルツハイマー型認知症
1アルツハイマー型認知症の特徴;加齢に伴う物忘れとの違い
2アルツハイマー型認知症の病態
3アルツハイマー型認知症の症状
4アルツハイマー型認知症の診断
5アルツハイマー型認知症の治療薬
脳血管性認知症
1脳血管性認知症の病態
2脳血管性認知症の症状
3脳血管性認知症の診断
4脳血管性認知症の治療
レビー小体型認知症
1レビー小体型認知症の病態
2レビー小体型認知症の症状と診断
3レビー小体型認知症の検査
4レビー小体型認知症の治療
前頭側頭型認知症
1前頭側頭型認知症の症状
2前頭側頭型認知症の治療
認知症の原因疾患の鑑別
うつ病の鑑別
せん妄の基礎知識と診断
1せん妄とは
2せん妄のタイプ
3せん妄の症状
4せん妄の診断
5せん妄と認知症、うつ病の鑑別診断
6せん妄の原因
7せん妄の治療
うつ病の基礎知識と診断
1うつ病の疫学・頻度
2うつ病の誘因
3うつ病になりやすい人格
4うつ病の症状
5うつ病の分類
6うつ病の病因
7うつ病の診断
8うつ病の治療
9うつ病の経過・予後
第4章 高齢者の理解
1時代と生活背景
2発達段階としての老年期とは
3老年期における心理的変化
4老年期における身体的変化
第5章 認知機能が低下している人のケアのポイント
1全身管理を怠らない
2環境へ適応できるようにする
3睡眠を確保する
4活動を妨げない
5心理的サポート
6わかりやすい説明
7持てる力を創造し個別のケアを
第6章 サポート事例とアプローチの実際
case1 身体疾患、 薬剤、 環境変化が関与して、せん妄になった患者さん
case2 こだ わりが 強く、 強 い 口 調 で訴えを繰り返 す 患 者さん
case3 身体の緊張が和らぎケ ア の 拒 否 が なくな っ た 患 者 さ ん
case4 認知機能検査によって、うつ病に加え認知症の存在が明らかになった患者さん
case5 適応障害となり「死にたい」と訴えた患者さん
case6 食事量が増えず、褥瘡治癒や離床、リハビリテーションが進まなかった患者さん
case7 「 病 棟 に 忘 れ 物 を し た 」と 訴 え る一 人 暮 らし の 患 者 さ ん
1医療の現状と多職種チーム活動
2当院における多職種チーム
33 D サ ポ ー ト チ ー ム 立 ち 上 げ の 経 緯 と そ の 効 果
4管理者として多職種チームを支援する
5「場」をつくり、「共体験」することで、「共感」の輪をつくる
6高齢者や認知症をもった人が安心して生きていける社会をめざして
第2章 3Dサポートチームとは
13D サポートチームの誕生の経緯
2活動内容
3多職種チームのメリット
4各専門領域の役割
1.リエゾンナースの役割
2.認知症看護認定看護師の役割
3.臨床心理士の役割
第3章 認知症・せん妄・うつ病の基礎知識と診断
認知症の基礎知識と診断
1認知症とは
2認知症の有病率
3認知症の症状
4認知症の診断
5認知症の原因疾患
6認知症の検査
アルツハイマー型認知症
1アルツハイマー型認知症の特徴;加齢に伴う物忘れとの違い
2アルツハイマー型認知症の病態
3アルツハイマー型認知症の症状
4アルツハイマー型認知症の診断
5アルツハイマー型認知症の治療薬
脳血管性認知症
1脳血管性認知症の病態
2脳血管性認知症の症状
3脳血管性認知症の診断
4脳血管性認知症の治療
レビー小体型認知症
1レビー小体型認知症の病態
2レビー小体型認知症の症状と診断
3レビー小体型認知症の検査
4レビー小体型認知症の治療
前頭側頭型認知症
1前頭側頭型認知症の症状
2前頭側頭型認知症の治療
認知症の原因疾患の鑑別
うつ病の鑑別
せん妄の基礎知識と診断
1せん妄とは
2せん妄のタイプ
3せん妄の症状
4せん妄の診断
5せん妄と認知症、うつ病の鑑別診断
6せん妄の原因
7せん妄の治療
うつ病の基礎知識と診断
1うつ病の疫学・頻度
2うつ病の誘因
3うつ病になりやすい人格
4うつ病の症状
5うつ病の分類
6うつ病の病因
7うつ病の診断
8うつ病の治療
9うつ病の経過・予後
第4章 高齢者の理解
1時代と生活背景
2発達段階としての老年期とは
3老年期における心理的変化
4老年期における身体的変化
第5章 認知機能が低下している人のケアのポイント
1全身管理を怠らない
2環境へ適応できるようにする
3睡眠を確保する
4活動を妨げない
5心理的サポート
6わかりやすい説明
7持てる力を創造し個別のケアを
第6章 サポート事例とアプローチの実際
case1 身体疾患、 薬剤、 環境変化が関与して、せん妄になった患者さん
case2 こだ わりが 強く、 強 い 口 調 で訴えを繰り返 す 患 者さん
case3 身体の緊張が和らぎケ ア の 拒 否 が なくな っ た 患 者 さ ん
case4 認知機能検査によって、うつ病に加え認知症の存在が明らかになった患者さん
case5 適応障害となり「死にたい」と訴えた患者さん
case6 食事量が増えず、褥瘡治癒や離床、リハビリテーションが進まなかった患者さん
case7 「 病 棟 に 忘 れ 物 を し た 」と 訴 え る一 人 暮 らし の 患 者 さ ん
続きを読む
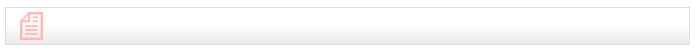
序文・はじめに・あとがき 等
3Dサポートチームが発生して結実し、終了したプロセスは、まさに横浜市 立みなと赤十字病院(以下、当院)の 10 年間の歴史そのものでした。当院が開 院したのは 2005(平成 17)年。そのころは、人々の医療に関する意識の変化や 治療の発展、医療事故・訴訟の増大などの要因で、医療および周辺業務が増大 し、とくに救急や産科、小児科を中心に勤務医が疲弊し、医療が崩壊寸前とマ スコミで大きく取り上げられた時代でした。
2 0 0 7( 平 成 1 9 )年 の 末 に 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知「 医 師 及 び 医 療 関 係 職 と 事 務職員等との間等での役割分担の推進について」が出され、メディカルクラー クや助産師、臨床検査技師等の役割拡大による医師の負担軽減の推進が示され ま し た 。 2 0 0 8( 平 成 2 0 )年 に は 厚 生 労 働 省 か ら の「 安 心 と 希 望 の 医 療 確 保 ビ ジ ョン」により薬剤師の役割拡大が示され、さらに同年の診療報酬改定で開業医 の役割拡大にも及びました。
2010(平成 22)年には厚生労働省チーム医療の推進に関する検討会の報告書 「チーム医療の推進について」が発表されました。そこにはチーム医療を「医療 に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情 報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確 に対応した医療を提供すること」と定義されました。この報告書では看護師や 薬剤師、リハビリテーション関係職種、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射 線技師、事務職員等(看護補助者・診療情報管理士等)の役割拡大が示されま した。これによりリハビリテーション関連職員の痰の吸引などは取り組まれた
施設もあると思います。 さらにその頃、医療スタッフ間の連携のあり方として「組織横断的な取り組
み」で多職種チームの活動を取り上げ、栄養サポート、感染制御、緩和ケア、 呼吸サポート、褥瘡対策などの多職種チーム活動が例示され、各施設が多職種 チームを次々と導入していきましたが、そこには続々と加算がついた診療報酬 のインセンティブが大きなきっかけとなったようです。
では、ほんとうに「診療報酬が付いたからチームはじめなさい」でよいので しょうか。自施設にとってこのチームは本当に必要か現場のニーズを見極める
ことが重要ではないでしょうか。答えは現場にあるのです。それでなくても忙しい医療者が多職種チーム活動を行うにはそれ相応の動機が必要ですし、メン
バーの献身のみに依存するのではなく、活動しやすく成果がでるように支援することが必要ではないでしょうか。それを病院管理者や部門・部署の管理者が
考え実践することでメンバーの動機づけや活動成果は高まると思います。管理
者の方も管理の視点で組織分析をしてニーズを把握し、できる範囲の効果的な
活動の形を多職種チームメンバーとともに決めていくことが必要です。
2 0 0 7( 平 成 1 9 )年 の 末 に 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知「 医 師 及 び 医 療 関 係 職 と 事 務職員等との間等での役割分担の推進について」が出され、メディカルクラー クや助産師、臨床検査技師等の役割拡大による医師の負担軽減の推進が示され ま し た 。 2 0 0 8( 平 成 2 0 )年 に は 厚 生 労 働 省 か ら の「 安 心 と 希 望 の 医 療 確 保 ビ ジ ョン」により薬剤師の役割拡大が示され、さらに同年の診療報酬改定で開業医 の役割拡大にも及びました。
2010(平成 22)年には厚生労働省チーム医療の推進に関する検討会の報告書 「チーム医療の推進について」が発表されました。そこにはチーム医療を「医療 に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情 報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確 に対応した医療を提供すること」と定義されました。この報告書では看護師や 薬剤師、リハビリテーション関係職種、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射 線技師、事務職員等(看護補助者・診療情報管理士等)の役割拡大が示されま した。これによりリハビリテーション関連職員の痰の吸引などは取り組まれた
施設もあると思います。 さらにその頃、医療スタッフ間の連携のあり方として「組織横断的な取り組
み」で多職種チームの活動を取り上げ、栄養サポート、感染制御、緩和ケア、 呼吸サポート、褥瘡対策などの多職種チーム活動が例示され、各施設が多職種 チームを次々と導入していきましたが、そこには続々と加算がついた診療報酬 のインセンティブが大きなきっかけとなったようです。
では、ほんとうに「診療報酬が付いたからチームはじめなさい」でよいので しょうか。自施設にとってこのチームは本当に必要か現場のニーズを見極める
ことが重要ではないでしょうか。答えは現場にあるのです。それでなくても忙しい医療者が多職種チーム活動を行うにはそれ相応の動機が必要ですし、メン
バーの献身のみに依存するのではなく、活動しやすく成果がでるように支援することが必要ではないでしょうか。それを病院管理者や部門・部署の管理者が
考え実践することでメンバーの動機づけや活動成果は高まると思います。管理
者の方も管理の視点で組織分析をしてニーズを把握し、できる範囲の効果的な
活動の形を多職種チームメンバーとともに決めていくことが必要です。
続きを読む
