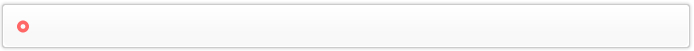
看護のための スラスラわかる薬のメカニズム
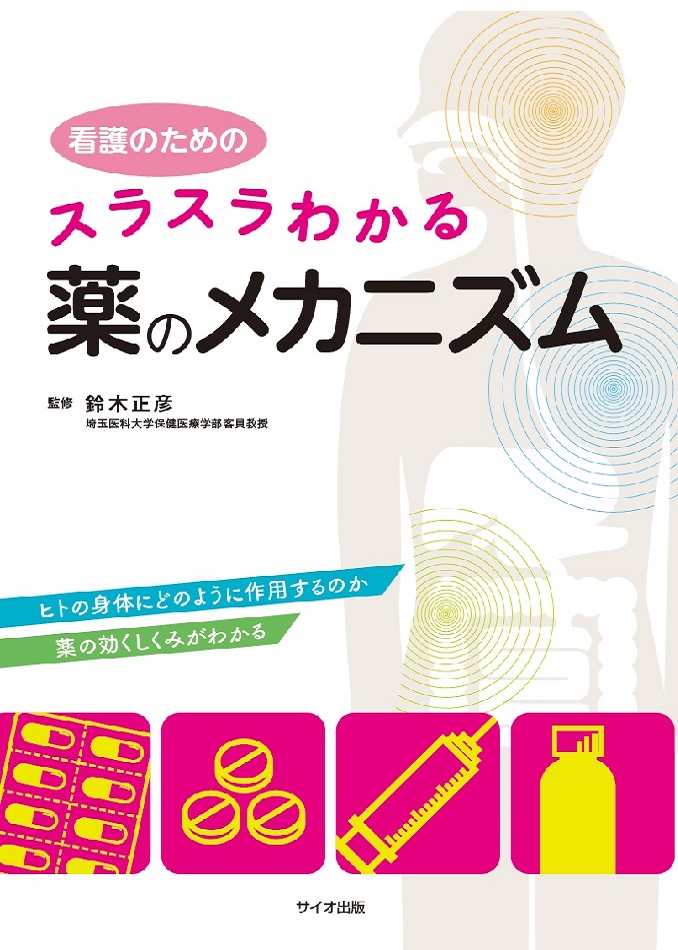 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
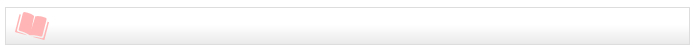
書籍概要
薬の知識の基礎のキソからわかりやすくに解説、メディカル全ての人に読んで欲しい。
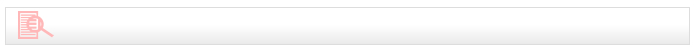
書籍目次詳細
第1部 薬とは何かを理解する
Chapter1 薬って何だろう 8
古代からあった「薬」/ 19 世紀に誕生した近代薬理学/医薬品医療機器等法で定められた医薬品/医薬品として許可されているのは約2万 3000種類/毒薬と劇薬/薬の使用目的は
4つ/医薬品とは、物質+情報である/やっかいな薬の名前
Chapter2 薬はどうして効くの? 14
薬は生体の生理機構を利用する/神経系、内分泌系、免疫系の働き/薬物が受容体と結合して反応が始まる/ストライカー(作動薬)とゴールキーパー(拮抗薬)
Chapter3 薬はどんな一生をたどる? 20
薬の運命も基本的には食べ物と同じ/薬の運命の分かれ道〜結合型と遊離型〜/生体に備わった薬物の関門/薬物代謝とは?/役目を終えた薬の行方/体内から薬が消えるまで
Chapter4 薬の効き方を左右する要因 26
適正な用量とは?/子どもの薬の量はどうやって計算する?/限界量を超えると、薬は毒にもなる/薬の形と吸収スピード/薬によって注射する部位は違う/薬を飲むタイミング
Chapter5 相互作用と副作用 36
薬の組み合わせによって効き方は違う/協力したり、反発したりする薬/相互作用が現れるポイント/相互作用を防ぐ方法は?
Chapter6 薬に有害作用とアレルギー 44
薬には必ず副作用がある/有害作用とは何か/薬物アレルギーが起こる機序/薬物依存とは、どういう状態を指すか
第2部 それぞれの薬を理解する
Chapter1 中枢神経に作用する薬 48
神経系の分類と呼び方/中枢神経系の働き/中枢神経系の情報伝達/向精神薬とは何か/正常な細胞に働き、異常な細胞の興奮をシャットアウトする抗てんかん薬/ドパミンを捕充する抗パーキンソン薬/痛みをとる薬〜全身麻酔と鎮痛薬〜/全身麻酔薬とは?/全身麻酔の種類/麻酔前投与とは?/麻酔性鎮痛薬とは?/そのほかの鎮痛薬
Chapter2 末梢神経系に作用する薬 70
情報を伝える末梢神経系の働き/交感神経と副交感神経が拮抗して支配する自律神経/キーワードは「アセチルコリン」/コリン作動薬や抗コリン薬が使用されるケース/「ノルアドレナリン」の放出/アドレナリン作動薬の使い方/抗アドレナリン薬の使い方/そのほかの遮断薬〜ニューロン遮断薬〜/骨格筋を支配する体性神経(運動神経)/筋肉を弛緩させる薬/局所麻酔/様々な局所麻酔
Chapter3 心臓・血管に作用する薬 83
24時間休みなく働き続ける心臓というポンプ/心筋に作用するジギタリス/ジギタリスの副作用/そのほかの強心薬/狭心症とは何か/狭心症の薬/不整脈とは何か/不整脈の薬/不整脈を抑える薬の分類/高血圧とは何か/血圧が上がる仕組み/血圧を下げる薬/脂質異常症とは何か/脂質異常症の薬
Chapter4 血液に関係する薬 98
血液の成分とは?/貧血とは何か/貧血の薬/白血球の異常とその薬/出血を止める薬/血液が固まらないようにする薬
Chapter5 呼吸器に作用する薬 105
空気も基本的には「異物」である/咳を止める薬/痰をとる薬/喘息とその薬
Chapter6 消化器に作用する薬 109
消化性潰瘍とは?/胃への攻撃を弱める薬/胃の防御を強くする薬/腸の運動と排便の仕組み/便秘が起こるメカニズム/便秘を止める薬の種類/下痢が起こるメカニズム/下痢を止める薬の種類
Chapter7 物質代謝に作用する薬 118
生体に必要な栄養素/糖質代謝のコントロールが効かない〜糖尿病〜/2つある糖尿病のタイプと治療薬/生体の基礎代謝を調節する甲状腺ホルモン/2つある甲状腺ホルモンの異常
/甲状腺機能亢進症の薬/甲状腺機能低下症の薬/骨を作るメカニズム/カルシウムの代謝異常〜骨粗鬆症〜/ビタミンの働き
Chapter8 化学療法薬 130
抗生物質の発見と化学療法/抗菌作用の仕組み/主な抗生物質とその適応/癌とは何か/細胞増殖標的型抗癌薬/それぞれの抗癌剤と作用する仕組み/分子標的薬/免疫抑制阻害薬
Chapter9アレルギーおよび炎症に関する薬 140
免疫反応とアレルギー/ヒスタミンを抑える薬とその仕組み/炎症とは何か/炎症を抑える薬のタイプ/ステロイド性抗炎症薬/非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の種類
参考文献 148
索引 149
Chapter1 薬って何だろう 8
古代からあった「薬」/ 19 世紀に誕生した近代薬理学/医薬品医療機器等法で定められた医薬品/医薬品として許可されているのは約2万 3000種類/毒薬と劇薬/薬の使用目的は
4つ/医薬品とは、物質+情報である/やっかいな薬の名前
Chapter2 薬はどうして効くの? 14
薬は生体の生理機構を利用する/神経系、内分泌系、免疫系の働き/薬物が受容体と結合して反応が始まる/ストライカー(作動薬)とゴールキーパー(拮抗薬)
Chapter3 薬はどんな一生をたどる? 20
薬の運命も基本的には食べ物と同じ/薬の運命の分かれ道〜結合型と遊離型〜/生体に備わった薬物の関門/薬物代謝とは?/役目を終えた薬の行方/体内から薬が消えるまで
Chapter4 薬の効き方を左右する要因 26
適正な用量とは?/子どもの薬の量はどうやって計算する?/限界量を超えると、薬は毒にもなる/薬の形と吸収スピード/薬によって注射する部位は違う/薬を飲むタイミング
Chapter5 相互作用と副作用 36
薬の組み合わせによって効き方は違う/協力したり、反発したりする薬/相互作用が現れるポイント/相互作用を防ぐ方法は?
Chapter6 薬に有害作用とアレルギー 44
薬には必ず副作用がある/有害作用とは何か/薬物アレルギーが起こる機序/薬物依存とは、どういう状態を指すか
第2部 それぞれの薬を理解する
Chapter1 中枢神経に作用する薬 48
神経系の分類と呼び方/中枢神経系の働き/中枢神経系の情報伝達/向精神薬とは何か/正常な細胞に働き、異常な細胞の興奮をシャットアウトする抗てんかん薬/ドパミンを捕充する抗パーキンソン薬/痛みをとる薬〜全身麻酔と鎮痛薬〜/全身麻酔薬とは?/全身麻酔の種類/麻酔前投与とは?/麻酔性鎮痛薬とは?/そのほかの鎮痛薬
Chapter2 末梢神経系に作用する薬 70
情報を伝える末梢神経系の働き/交感神経と副交感神経が拮抗して支配する自律神経/キーワードは「アセチルコリン」/コリン作動薬や抗コリン薬が使用されるケース/「ノルアドレナリン」の放出/アドレナリン作動薬の使い方/抗アドレナリン薬の使い方/そのほかの遮断薬〜ニューロン遮断薬〜/骨格筋を支配する体性神経(運動神経)/筋肉を弛緩させる薬/局所麻酔/様々な局所麻酔
Chapter3 心臓・血管に作用する薬 83
24時間休みなく働き続ける心臓というポンプ/心筋に作用するジギタリス/ジギタリスの副作用/そのほかの強心薬/狭心症とは何か/狭心症の薬/不整脈とは何か/不整脈の薬/不整脈を抑える薬の分類/高血圧とは何か/血圧が上がる仕組み/血圧を下げる薬/脂質異常症とは何か/脂質異常症の薬
Chapter4 血液に関係する薬 98
血液の成分とは?/貧血とは何か/貧血の薬/白血球の異常とその薬/出血を止める薬/血液が固まらないようにする薬
Chapter5 呼吸器に作用する薬 105
空気も基本的には「異物」である/咳を止める薬/痰をとる薬/喘息とその薬
Chapter6 消化器に作用する薬 109
消化性潰瘍とは?/胃への攻撃を弱める薬/胃の防御を強くする薬/腸の運動と排便の仕組み/便秘が起こるメカニズム/便秘を止める薬の種類/下痢が起こるメカニズム/下痢を止める薬の種類
Chapter7 物質代謝に作用する薬 118
生体に必要な栄養素/糖質代謝のコントロールが効かない〜糖尿病〜/2つある糖尿病のタイプと治療薬/生体の基礎代謝を調節する甲状腺ホルモン/2つある甲状腺ホルモンの異常
/甲状腺機能亢進症の薬/甲状腺機能低下症の薬/骨を作るメカニズム/カルシウムの代謝異常〜骨粗鬆症〜/ビタミンの働き
Chapter8 化学療法薬 130
抗生物質の発見と化学療法/抗菌作用の仕組み/主な抗生物質とその適応/癌とは何か/細胞増殖標的型抗癌薬/それぞれの抗癌剤と作用する仕組み/分子標的薬/免疫抑制阻害薬
Chapter9アレルギーおよび炎症に関する薬 140
免疫反応とアレルギー/ヒスタミンを抑える薬とその仕組み/炎症とは何か/炎症を抑える薬のタイプ/ステロイド性抗炎症薬/非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の種類
参考文献 148
索引 149
続きを読む
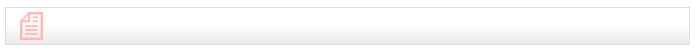
序文・はじめに・あとがき 等
はじめに
皆さん方が体調を崩し病院にかかった時のことを考えてみてください。検査、診察のあと、ほとんどの場合に薬が処方されます。このことからもわかるように、現代の医療では病気の治療のために薬物療法が重要な役割を果たしていることは、疑いの余地がありません。そのため、医療関係者にとって薬の知識は必須のものとなっています。しかし、その一方で、(公財)日本医療機能評価機構のまとめた2018年の全国652施設のヒヤリ・ハット事例のうち、薬によるものが37.9%(11,770件)を占め、事例の一位になっています。つまり、医療関係者は薬のより正しい知識を身につけることが求められます。
しかしながら、薬理学は勉強する学生の苦手な科目の1つにあげられています。薬の種類が多く、
カタカナ表記であること、薬の作用を理解するために、生化学や生理学などの知識が必要になってくることなどが関係していると思われます。
薬の正しい知識が必要なことはわかっているが、とっつきにくい、理解しにくい、覚えることが多すぎるという方に、まず手始めに読む本としての形態を考え、本書のような形になりました。第1部で「薬とは何?」ということを解説し、第2部で「それぞれの薬」を説明しています。取り上げた薬は代表的なものだけです。
本書で薬理学の概要を理解し、臨床実習等でわからない薬がでてきたら、医薬品集や詳しく説明した薬理学の成書を調べてください。参考図書を巻末に記載しましたので、利用してください。基本的な内容は本書で理解していますので、一見難解な本の内容がすいすいと頭に入ってくるはずです。そのようにして知識を増やし、その成果をぜひ医療の現場で活かしてください。
2019年7月
埼玉医科大学保健医療学部客員教授 鈴木正彦
皆さん方が体調を崩し病院にかかった時のことを考えてみてください。検査、診察のあと、ほとんどの場合に薬が処方されます。このことからもわかるように、現代の医療では病気の治療のために薬物療法が重要な役割を果たしていることは、疑いの余地がありません。そのため、医療関係者にとって薬の知識は必須のものとなっています。しかし、その一方で、(公財)日本医療機能評価機構のまとめた2018年の全国652施設のヒヤリ・ハット事例のうち、薬によるものが37.9%(11,770件)を占め、事例の一位になっています。つまり、医療関係者は薬のより正しい知識を身につけることが求められます。
しかしながら、薬理学は勉強する学生の苦手な科目の1つにあげられています。薬の種類が多く、
カタカナ表記であること、薬の作用を理解するために、生化学や生理学などの知識が必要になってくることなどが関係していると思われます。
薬の正しい知識が必要なことはわかっているが、とっつきにくい、理解しにくい、覚えることが多すぎるという方に、まず手始めに読む本としての形態を考え、本書のような形になりました。第1部で「薬とは何?」ということを解説し、第2部で「それぞれの薬」を説明しています。取り上げた薬は代表的なものだけです。
本書で薬理学の概要を理解し、臨床実習等でわからない薬がでてきたら、医薬品集や詳しく説明した薬理学の成書を調べてください。参考図書を巻末に記載しましたので、利用してください。基本的な内容は本書で理解していますので、一見難解な本の内容がすいすいと頭に入ってくるはずです。そのようにして知識を増やし、その成果をぜひ医療の現場で活かしてください。
2019年7月
埼玉医科大学保健医療学部客員教授 鈴木正彦
続きを読む
